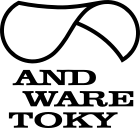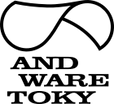Collections
-

HASAMI PORCELAIN
篠本拓宏(tortoise)のディレクションにより生まれた長崎波佐見町の波佐見焼による磁器の食器たち。 日本の伝統的な形態の根本でもある、潔くすっきりとした直線。機能と製造工程の必然性から導かれた、意味のある曲線。 シンプルな線のみで構成されているHASAMI PORCELAINのデザインは、いくつもの器が重なり合い、フォルムがリピートすることで、いっそう美しい調和をつくり出す。 20世紀に登場したモダンデザインのマスターピースを基礎としている為、無駄のない佇まいに普遍性が宿っている。
-
SAKUZAN - NOBUT
美濃焼の名窯元である SAKUZAN/作山窯さまと。 同窯は日本でも名のあるブランドなどの別注を手がけています。 型で制作された誤差の少ない食器たちは思わずシリーズで集めたくなります。 SAKUZANの食器は美しくシンプル、そしてコストパフォーマンスにも優れています。
-

SAKUZAN - Stripe
美濃焼の名窯元である SAKUZAN/作山窯さま。 同窯は日本でも名のあるブランドなどの別注を手がけています。 型で制作された誤差の少ない食器たちは思わずシリーズで集めたくなります。 SAKUZANの食器は美しくシンプル、そしてコストパフォーマンスにも優れています。
-
SUGATA
新潟県燕市で高級カトラリーをメインに製造するSUGATA。 2020年東京五輪・パラリンピックの選手村の食堂で採用されたことをきっかけに一躍脚光を浴びることになったブランドです。 黒いカトラリーは超極薄の酸化皮膜を幾層にも分けて加工することにより、見る角度によって色が変化します。 白いカトラリーはきめ細かくサンドブラストされており、手にしっくりと収まるような造作となっています。 燕市の高い技術力が分かる、ハイクオリティなカトラリーとなっています。
-
中村桜士
沖縄で活躍する陶芸家 中村桜士さん。 マンガンの濃いダークブラウン色や、相反する、クリーム色の釉薬。 沖縄の焼き物と言えばやちむんですが、中村さんは元々東京で作陶されていたこともあり、どこか都会的な洗練さを感じます。 ツルッとした釉薬は、あらゆるお料理を美しく魅せてくれます。
-
中村桜士
沖縄の土を求め、東京から移住し作陶される陶芸家 中村桜士さん。 土感溢れるワイルドな作風から、きめ細かいインダストリアルな作風まで、広いジャンルをカバーする手腕が特徴です。 広大な沖縄の海を眺めながら、今日も工房では静かに轆轤が回っています。